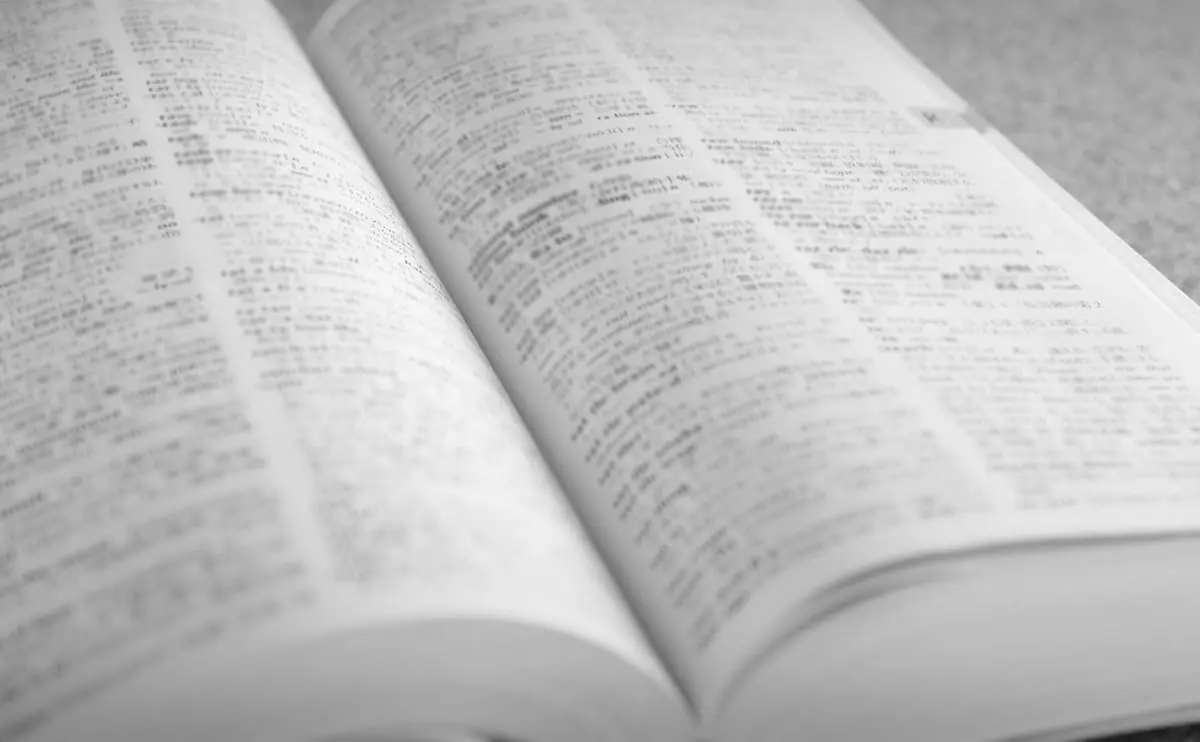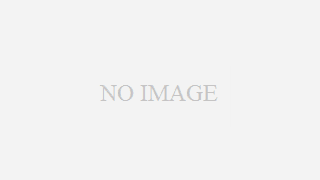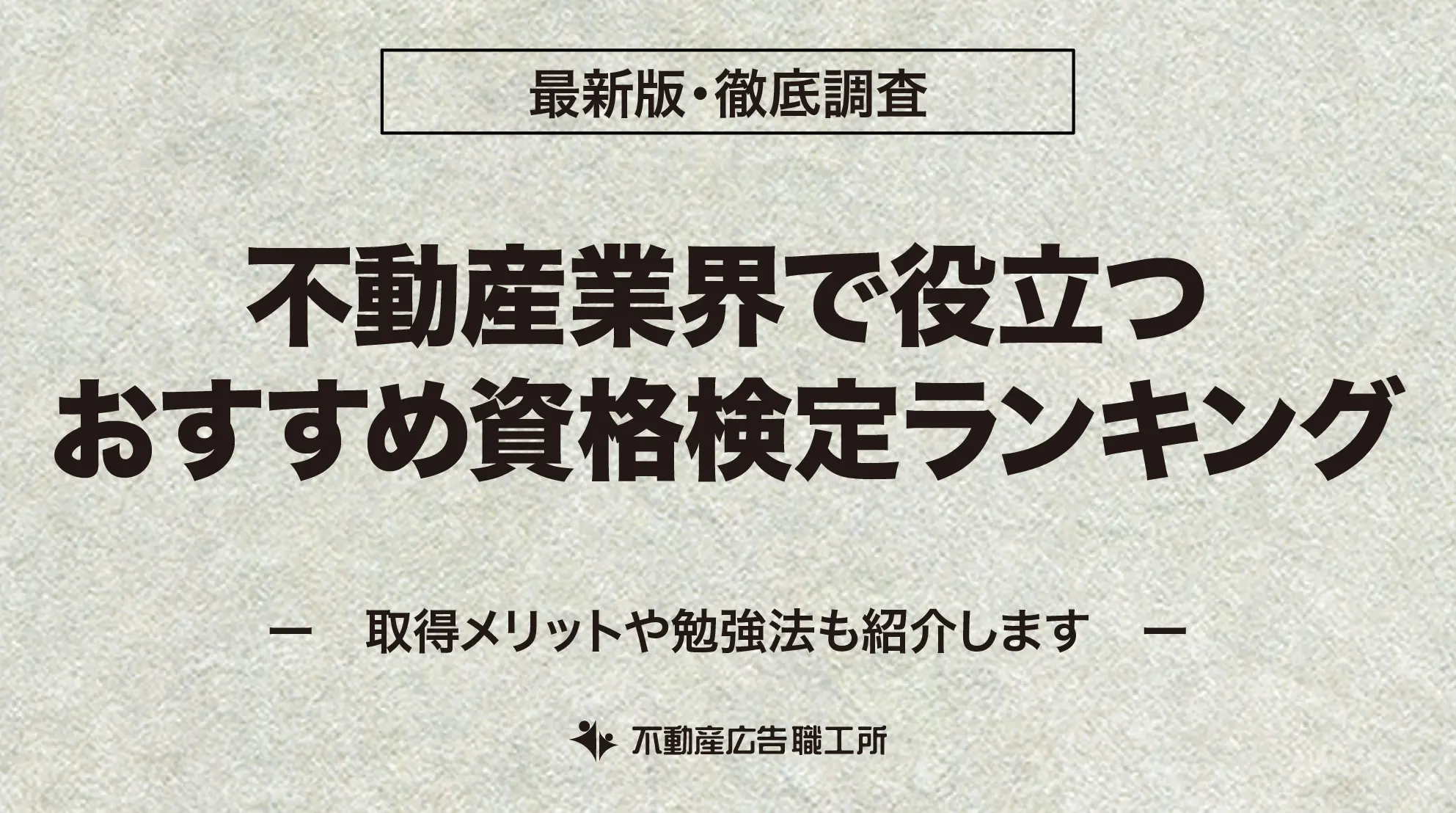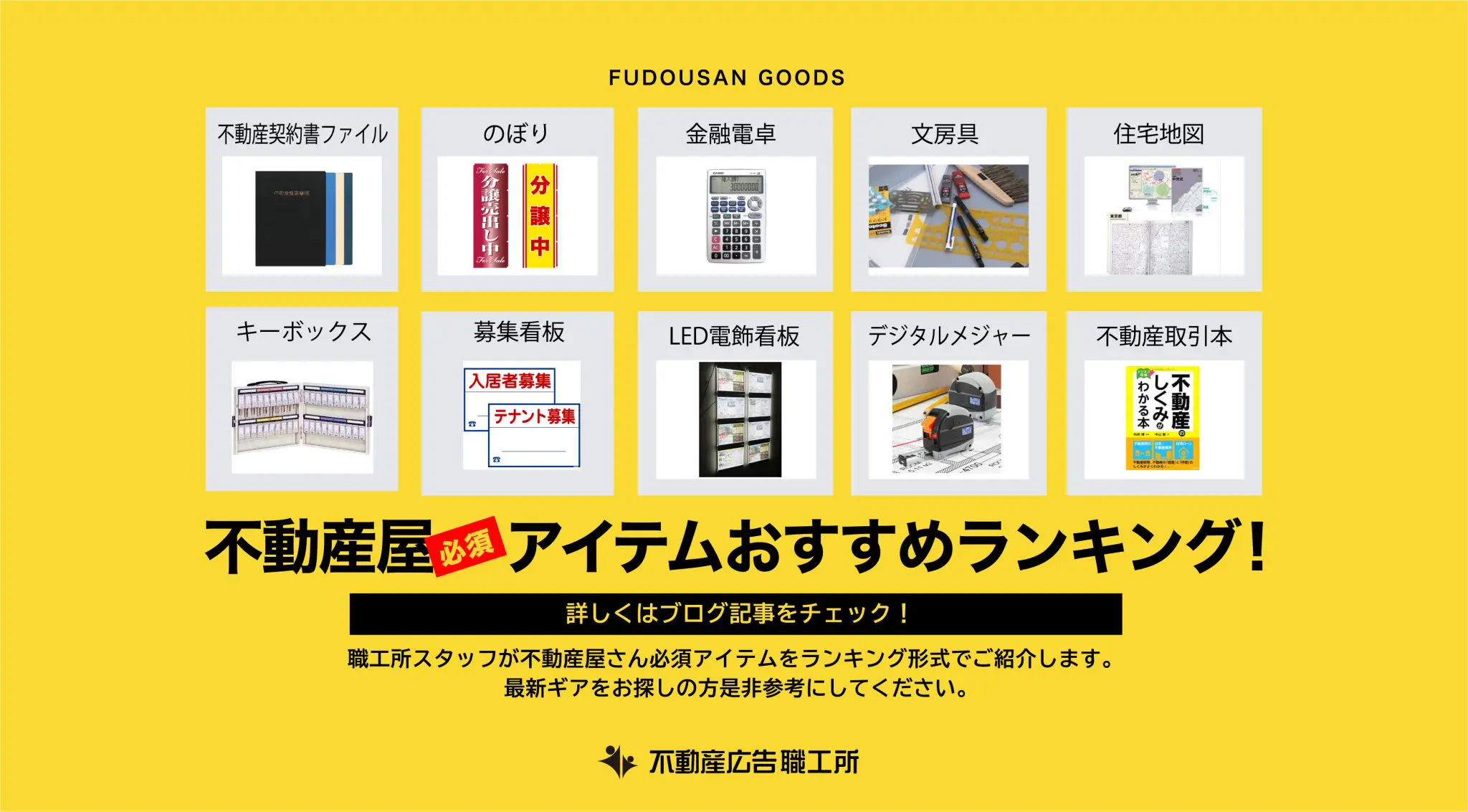環境にかかる負荷が大きいものに対して税金の負担を重くするものです。
化石燃料等に対する課税によって二酸化炭素などの排出量を抑える効果があるとされ、「炭素税」等の導入について議論されていますが、これも環境税の一種です。
環境税は、単に環境対策のための財源を確保するためのものではありません。
環境税の経済理論的な背景として、「ピグー税」と「ボーモル・オーツ税」という2つの考え方があります。
1.ピグー税
経済活動に伴う環境負荷などについては、その影響について負担がなされていないため、膨大な生産・消費が促進されることになります。
そこで、活動に課税することによって市場機能の適正化を図ることができるという考え方があります。
このような考え方に基づく政策を外部不経済の内部化といいます。
この種の生産物課税は、提唱者のA.C.ピグーにちなんでピグー税と呼ばれます。
2.ボーモル・オーツ税
ピグー税の導入については、現実的には困難であることが多いです。
その理由は、外部不経済を具体的に計測することが難しいことなどがあります。
そこで、ピグー税に代わって、汚染物質の排出に対して課税することで、汚染物質の排出量を制御するという手法が提案されました。
これを、ボーモル・オーツ税といいます。
現在導入が議論されている環境税は、このボーモル・オーツ税の性格が強いです。
なお、環境税を、税収目的で徴収される環境に関わる税金として捉える考え方もあり、そのような広義の環境税としては、産業廃棄物税や森林環境税があります。
これらの税制度は、一部の地方公共団体が導入しています。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)