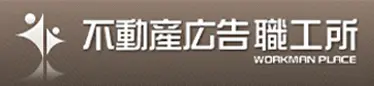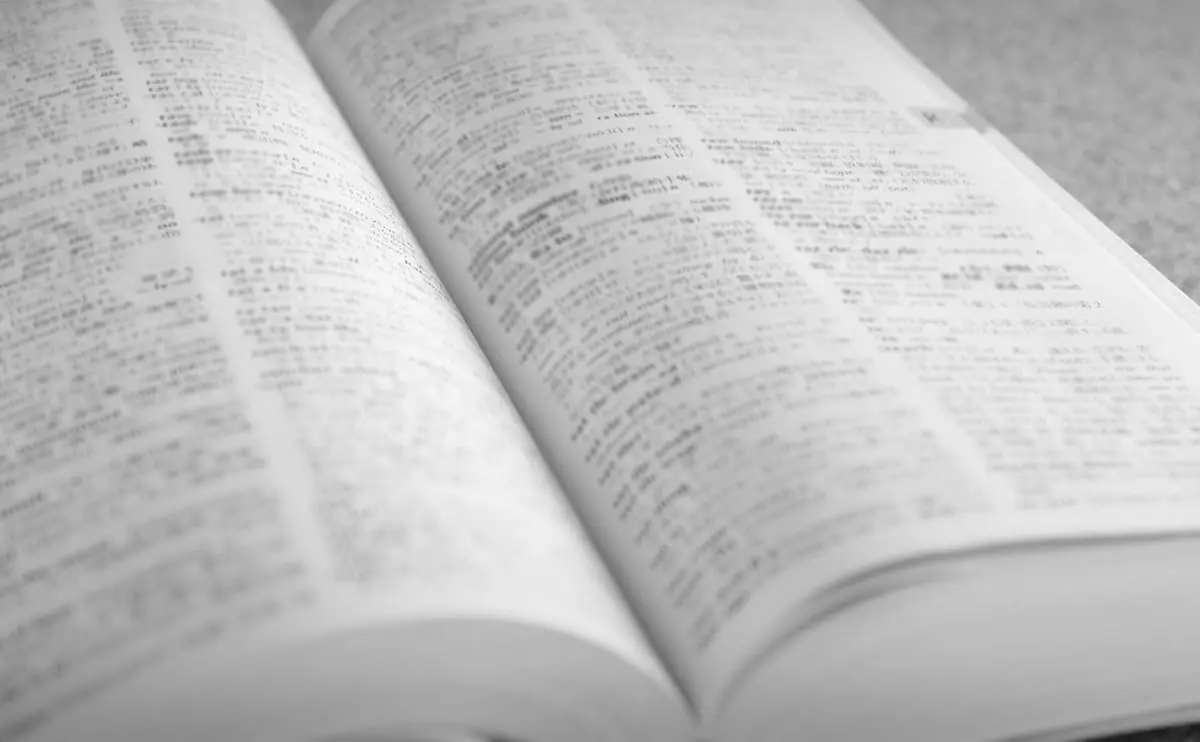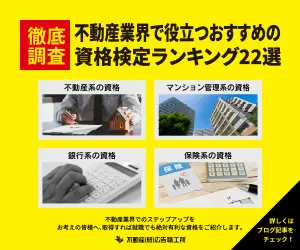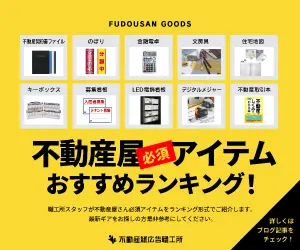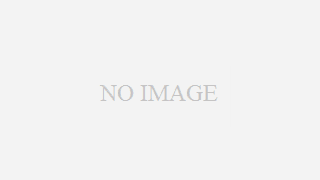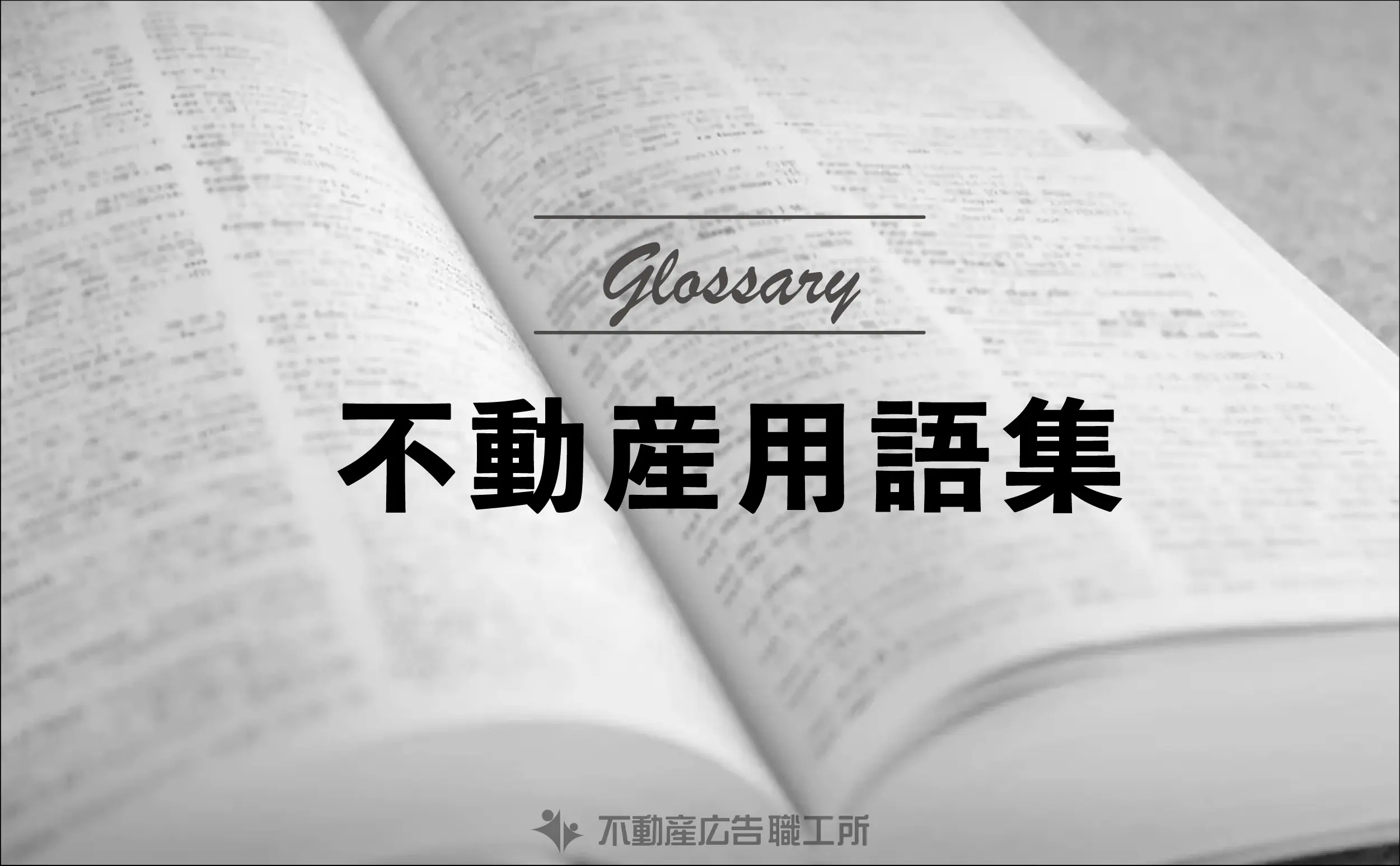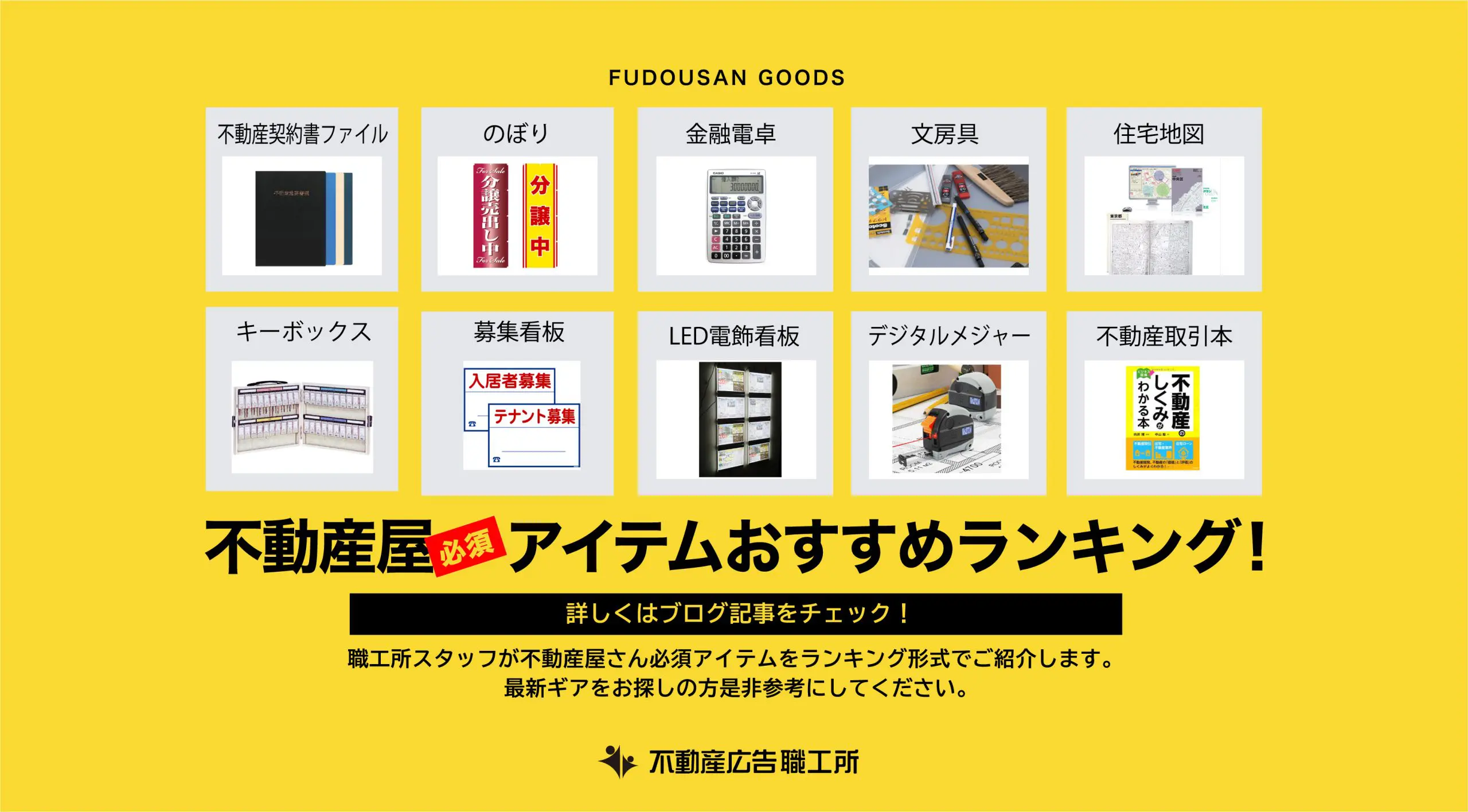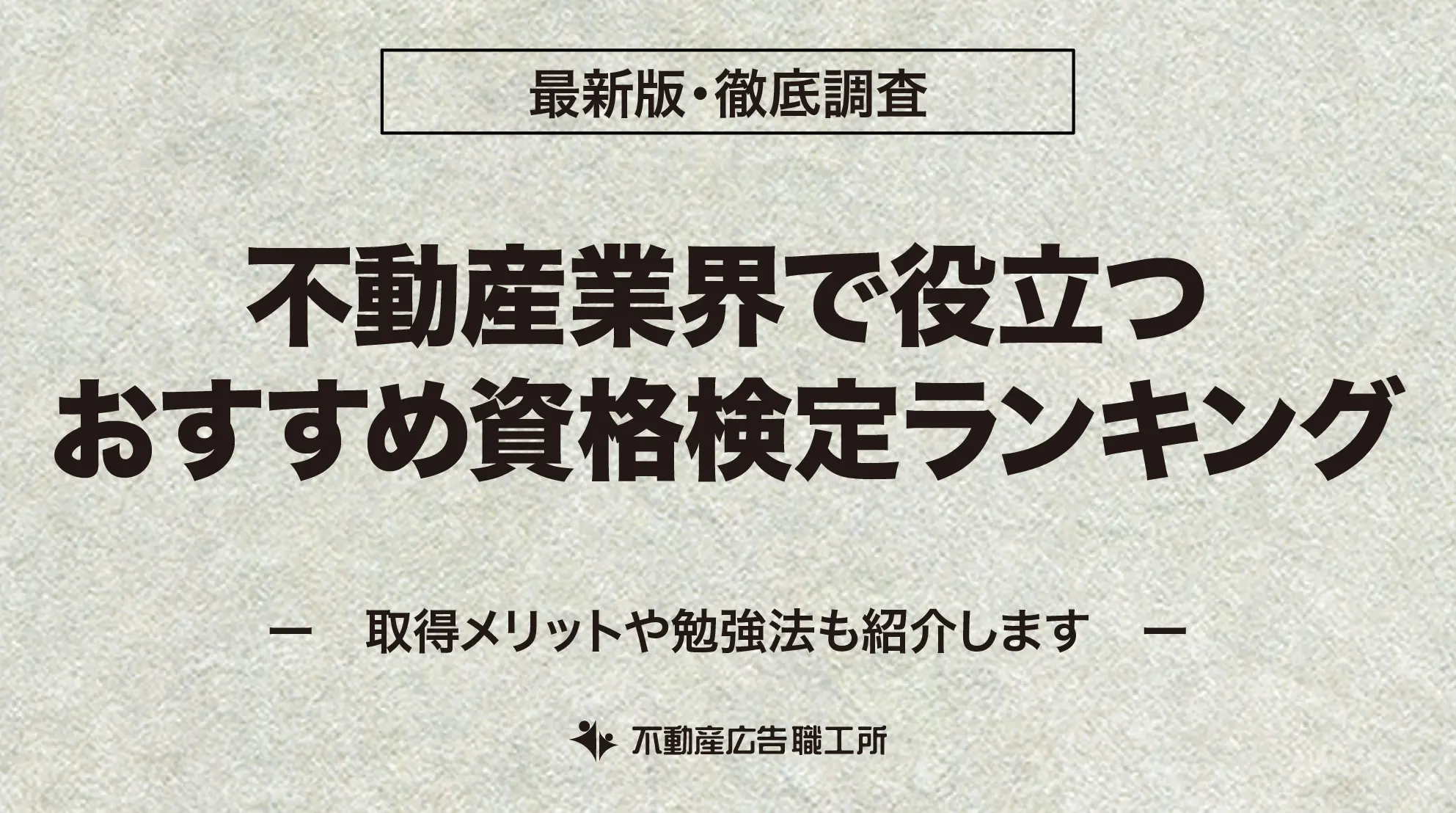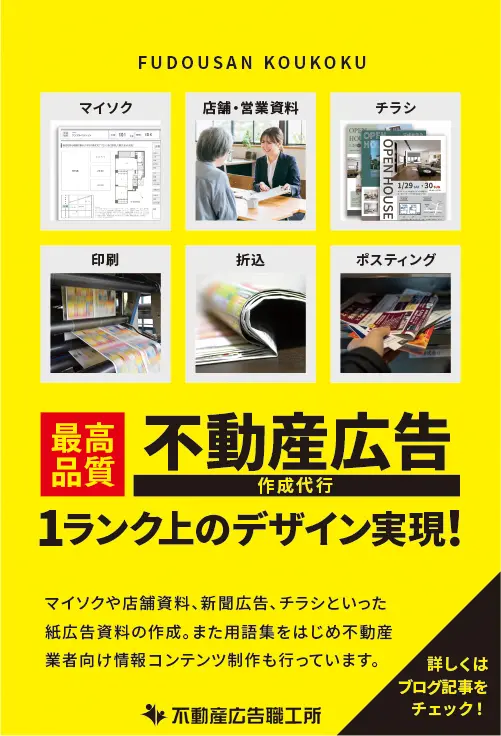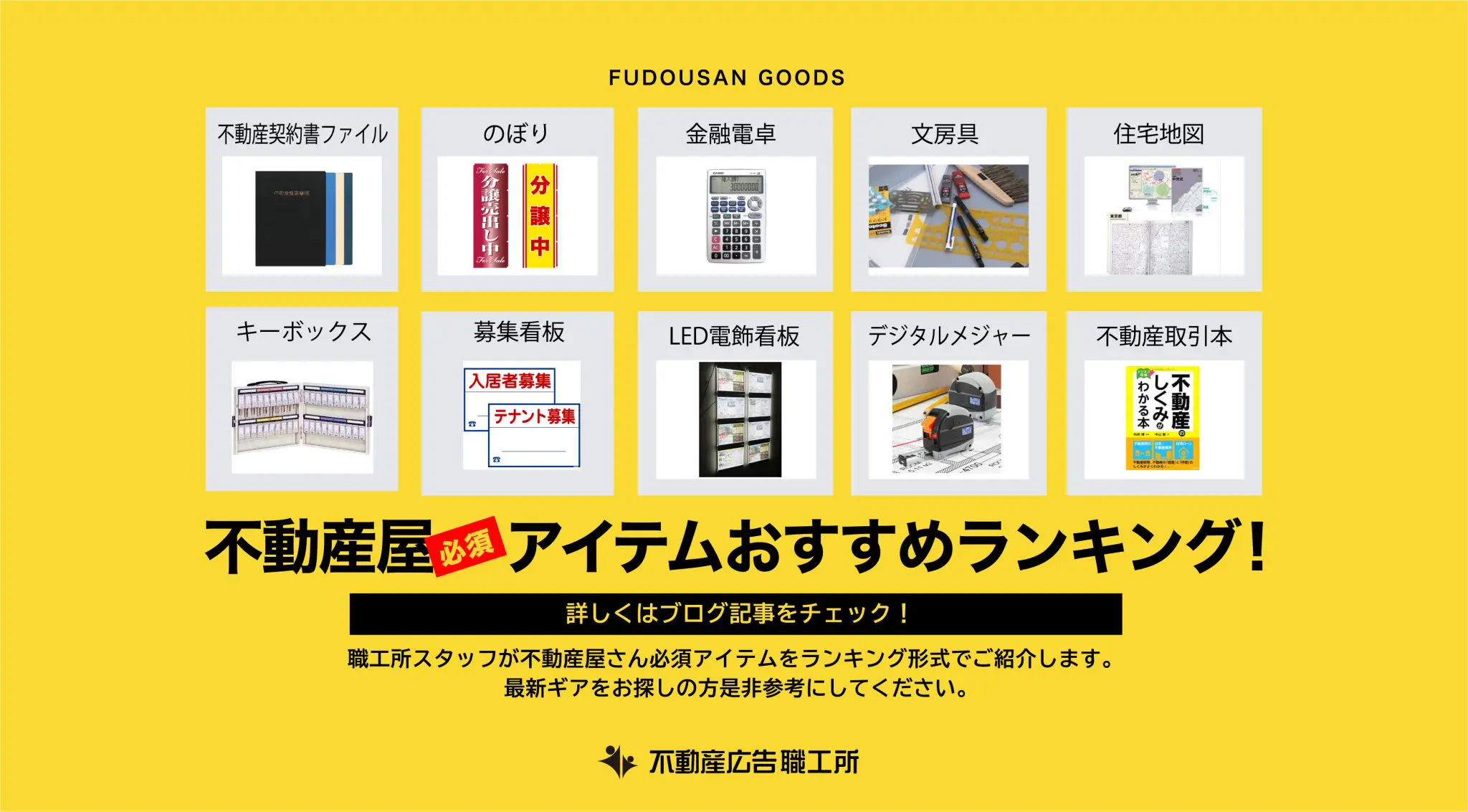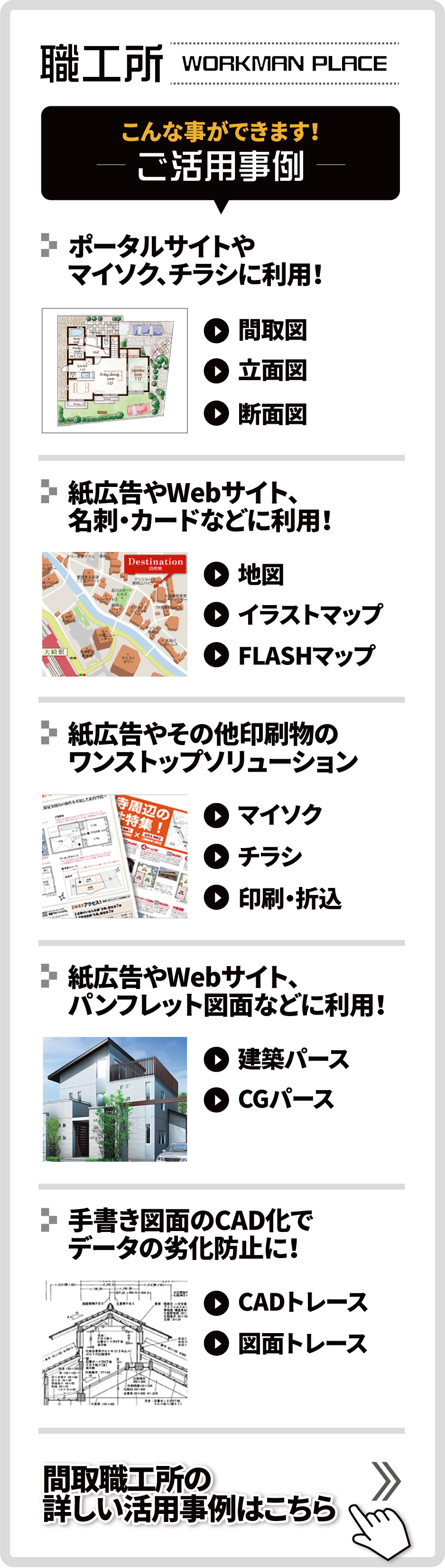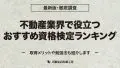主に関東地方で用いられてきた、伝統家屋の基本モジュールを「関東間」または「「田舎間」」といいます。
京間と比べると面積がやや狭いです。
伝統家屋の設計時に基本となる柱の間隔のことを「1間(いっけん)」といいます。
関東間とは、この1間を「6尺」(約181.2cm)とする家屋のことです。
(注)
日本古来の度量衡である尺貫法では、1尺は30.303cm、1寸は1尺の10分の1、1分は1尺の100分の1となっています。
なお、尺の長さは1891(明治24)年の度量衡法で定められたが、1958(昭和33)年に公式の単位としては廃止され、メートル法で表記されるようになりました。
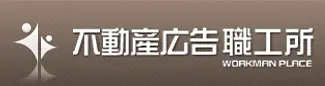
![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)