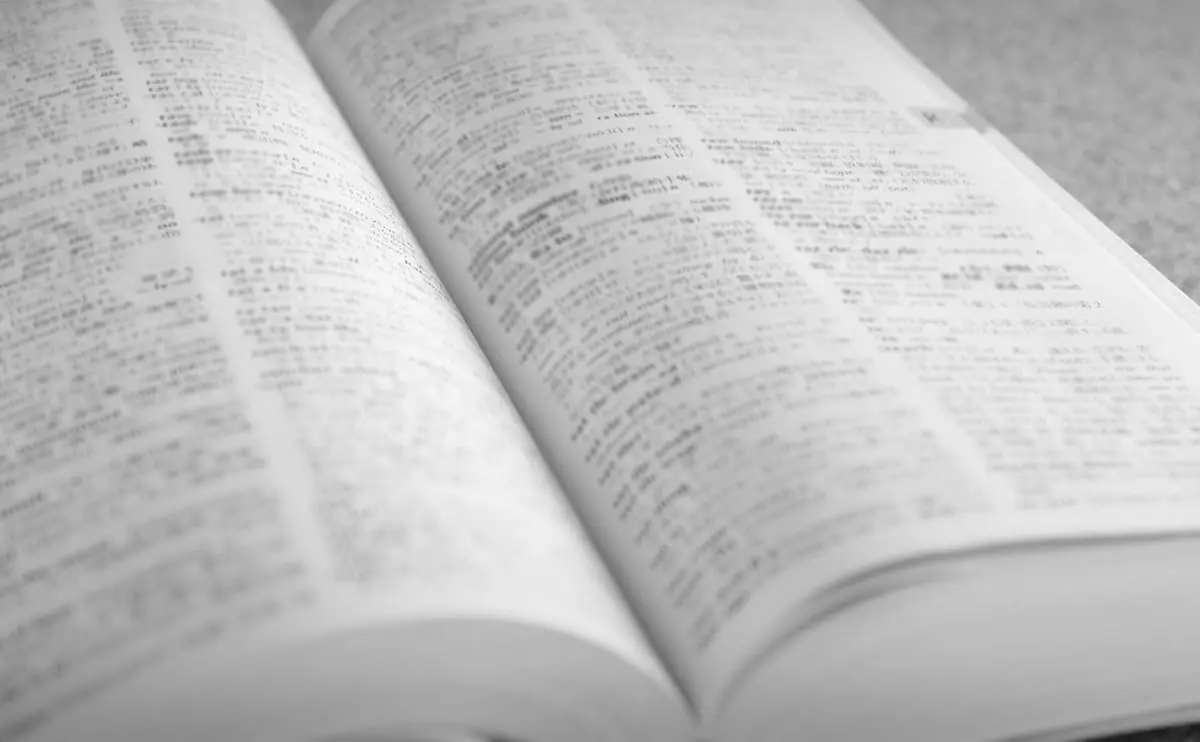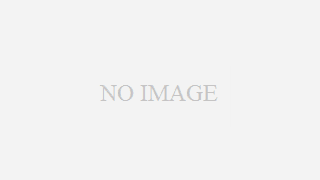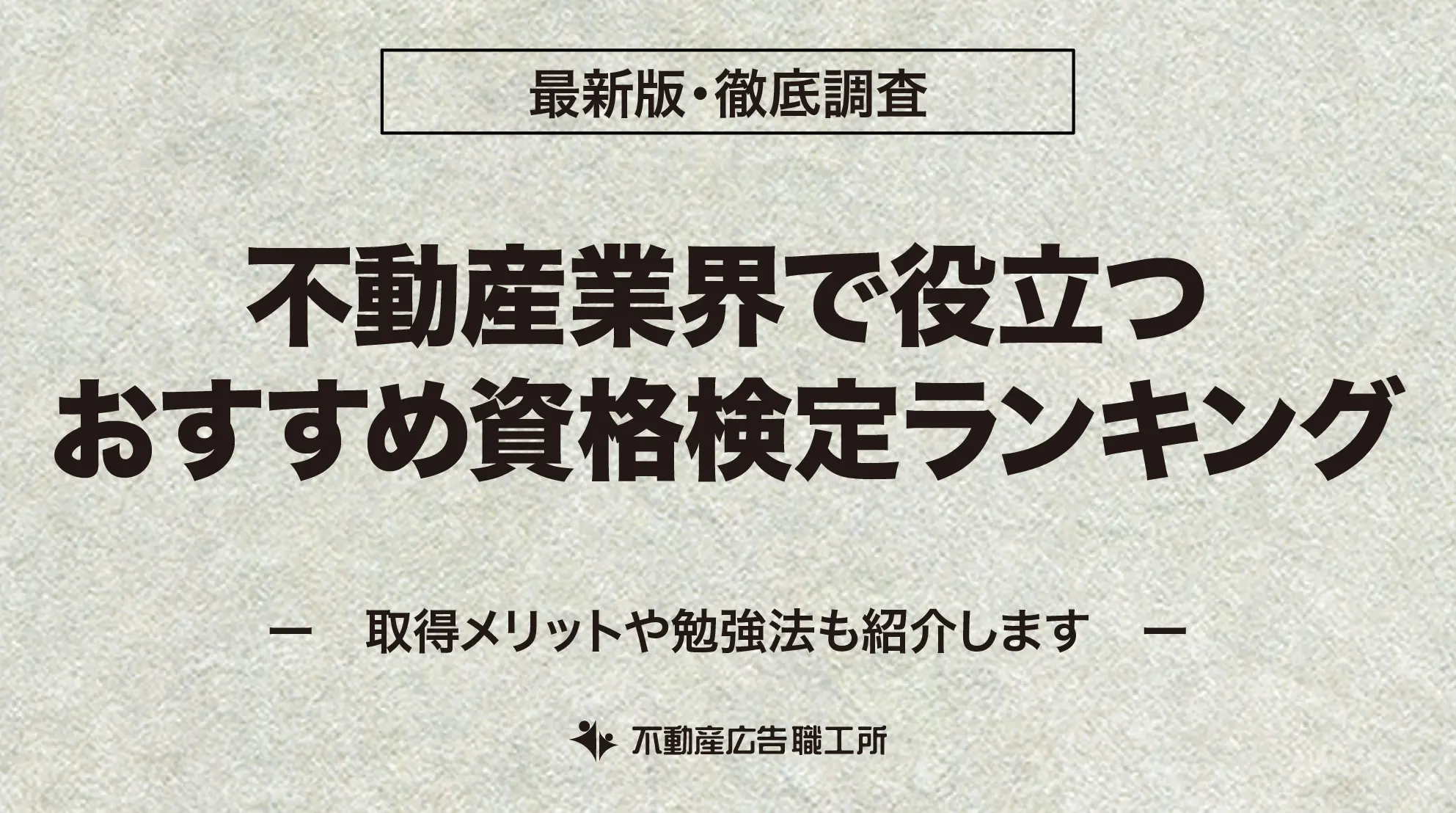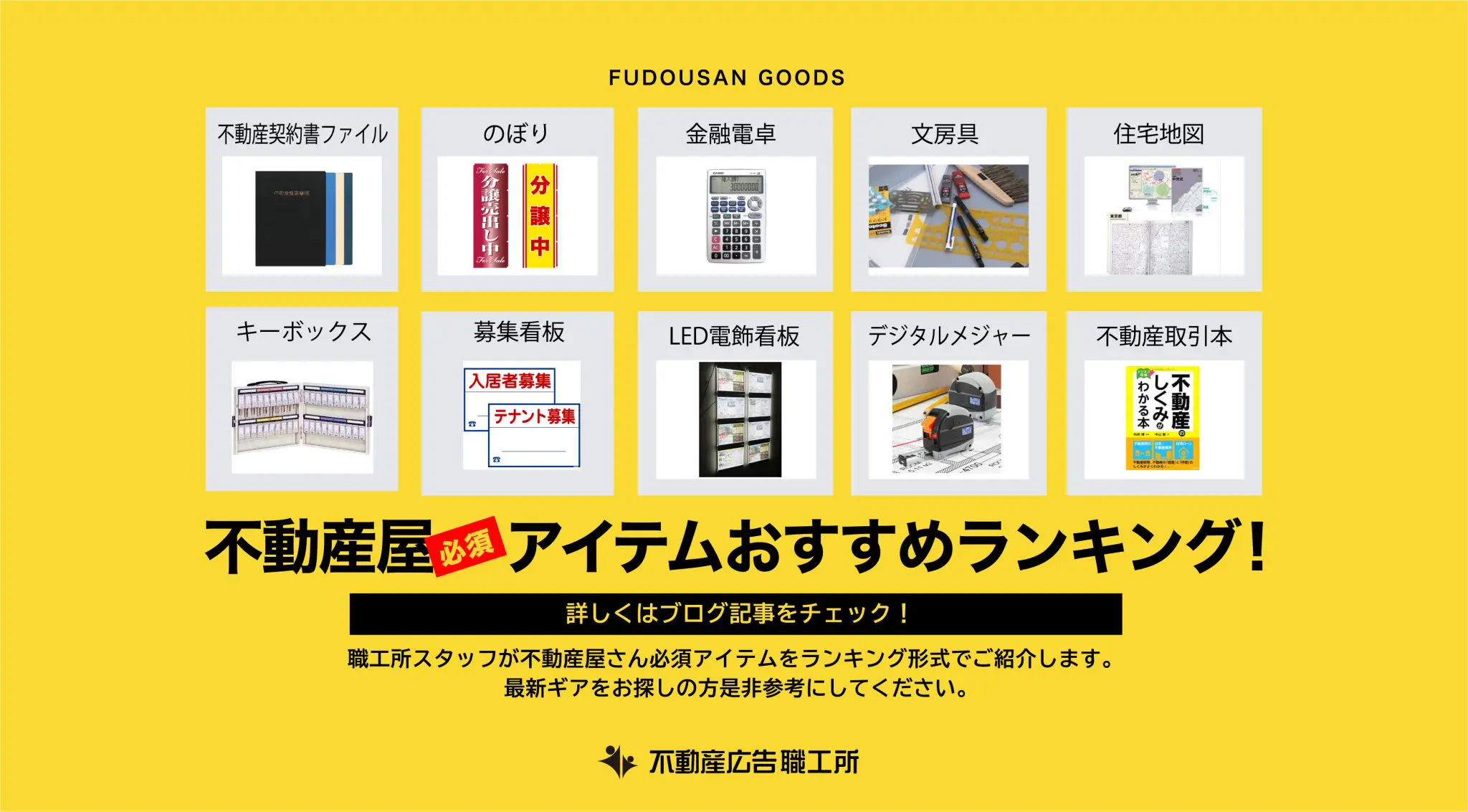設計住宅性能評価書とは、住宅性能表示制度に基づき、客観的な第三者評価機関によって、建物の設計段階において、一定の性能水準に達していることが認められた住宅に交付されるものをいいます(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第3条)。
住宅品質確保法では、設計住宅性能評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しています。いわゆる住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされます。また、新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされるという意味です(住宅の品質確保の促進等に関する法律6条1項、2項)。この規定によって注文者保護・買主保護が図られています(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。尚、住宅性能評価には、施工段階と完成段階での検査の評価結果をまとめた建設住宅性能評価書もあり、通常は設計と建設の住宅性能評価書をあわせて取得するのが一般的です。
ただし、上記の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用されません(同法6条4項)。
このような設計住宅性能評価書が作成される手順は下記のとおりです。
1.作成の依頼
新築住宅の請負人または注文者(もしくは新築住宅を売却する売主または買主)が、登録住宅性能評価機関に対して、設計住宅性能評価書の作成を依頼します(同法施行規則第3条)。
この評価書作成には10万円から30万円程度の費用が掛かるといわれていますが、その費用は請負人または注文者(もしくは売主または買主)が負担することになります。
尚、建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある既存住宅については、設計住宅性能評価書の作成を依頼することは出来ません。
2.必要な書類の提出
依頼者は、設計住宅性能評価書を作成するために、登録住宅性能評価機関に対して、必要な関係書類を提出する必要がありますが、この依頼者が提出すべき書類は、配置図・仕様書・各階平面図など非常に多岐に渡ります。これは国土交通省告示「設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件」により定められています。
3.設計住宅性能評価書の作成
登録住宅性能評価機関は提出された多数の書類をもとに、国土交通大臣が定めた基準に照らし合わせて新築住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を作成します(評価する項目の詳細は「日本住宅性能表示基準」へ)。
このように設計住宅性能評価書は、あくまで設計図等の書面のみにもとづく評価結果であって、現地で住宅を検査した結果にもとづく評価ではありません。
そのため、検査結果にもとづく住宅性能評価書の作成を希望する場合には、請負人・注文者(もしくは売主・買主)が、登録住宅性能評価機関に対して建設住宅性能評価書の作成を、別途依頼する必要があります(同法施行規則第5条)。
このようにして依頼者の費用負担で作成された設計住宅性能評価書を、実際に請負契約書・売買契約書に添付等するかどうかは請負人・売主の自由に委ねられています(同法第6条)。
また、住宅性能表示制度ですが、住宅の性能に関して、耐震等級などの構造の安定や、省エネルギー対策等級などの温熱環境等、10分野29事項に渡って評価基準が定められています。それにしたがって指定住宅性能評価機関が客観的な評価を行います。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)