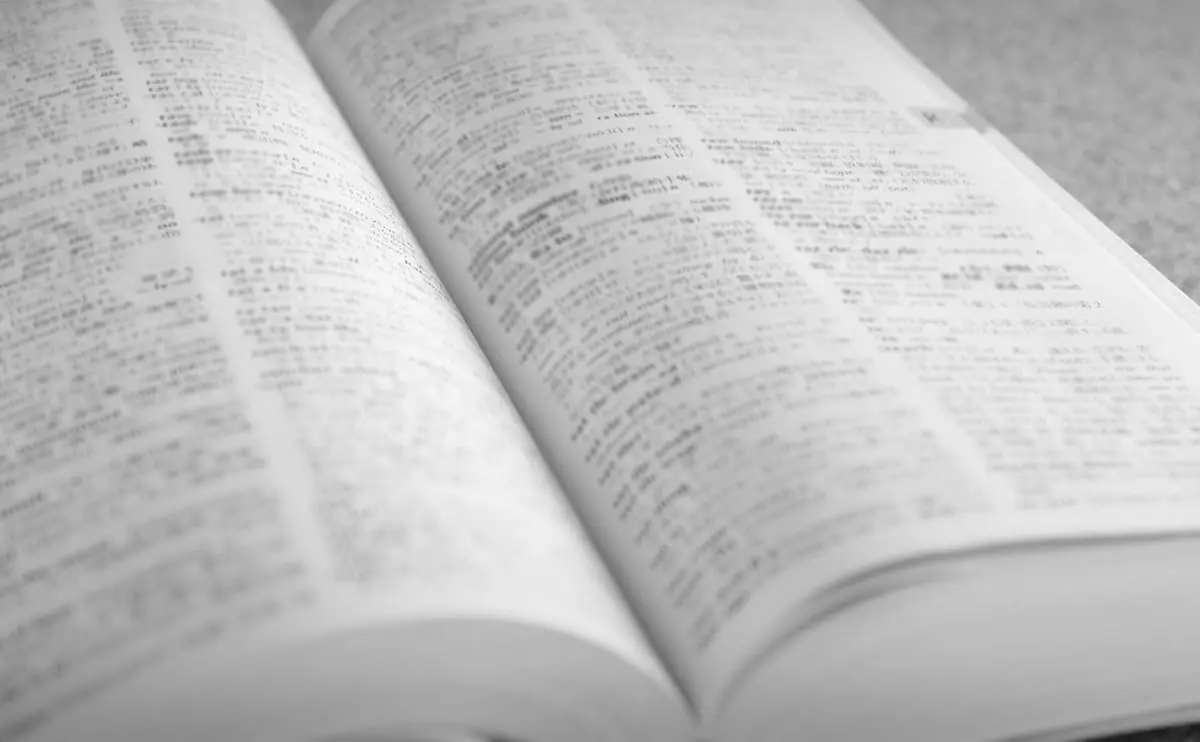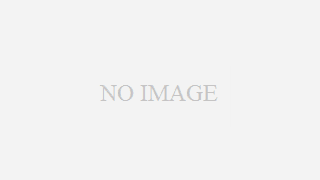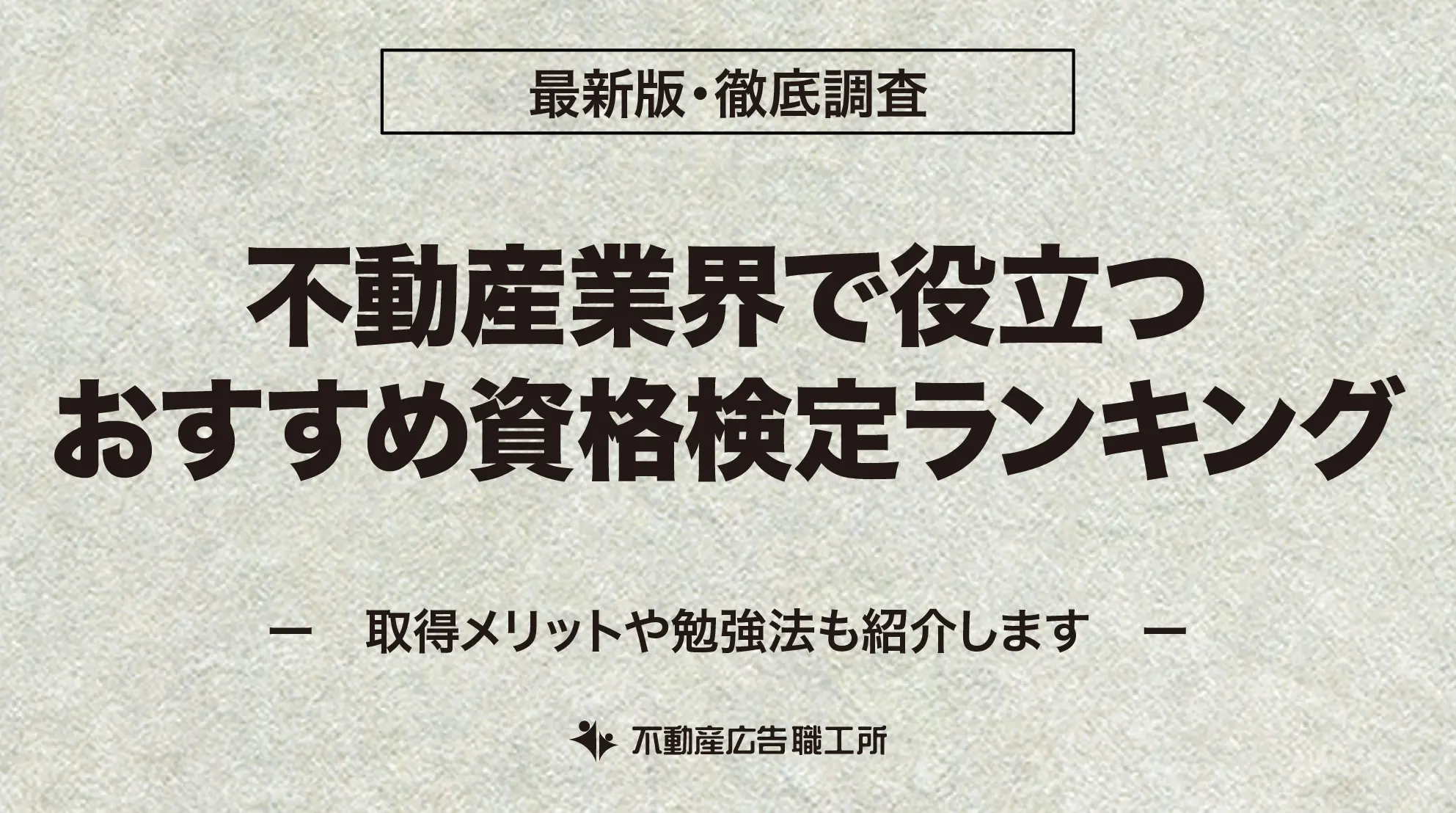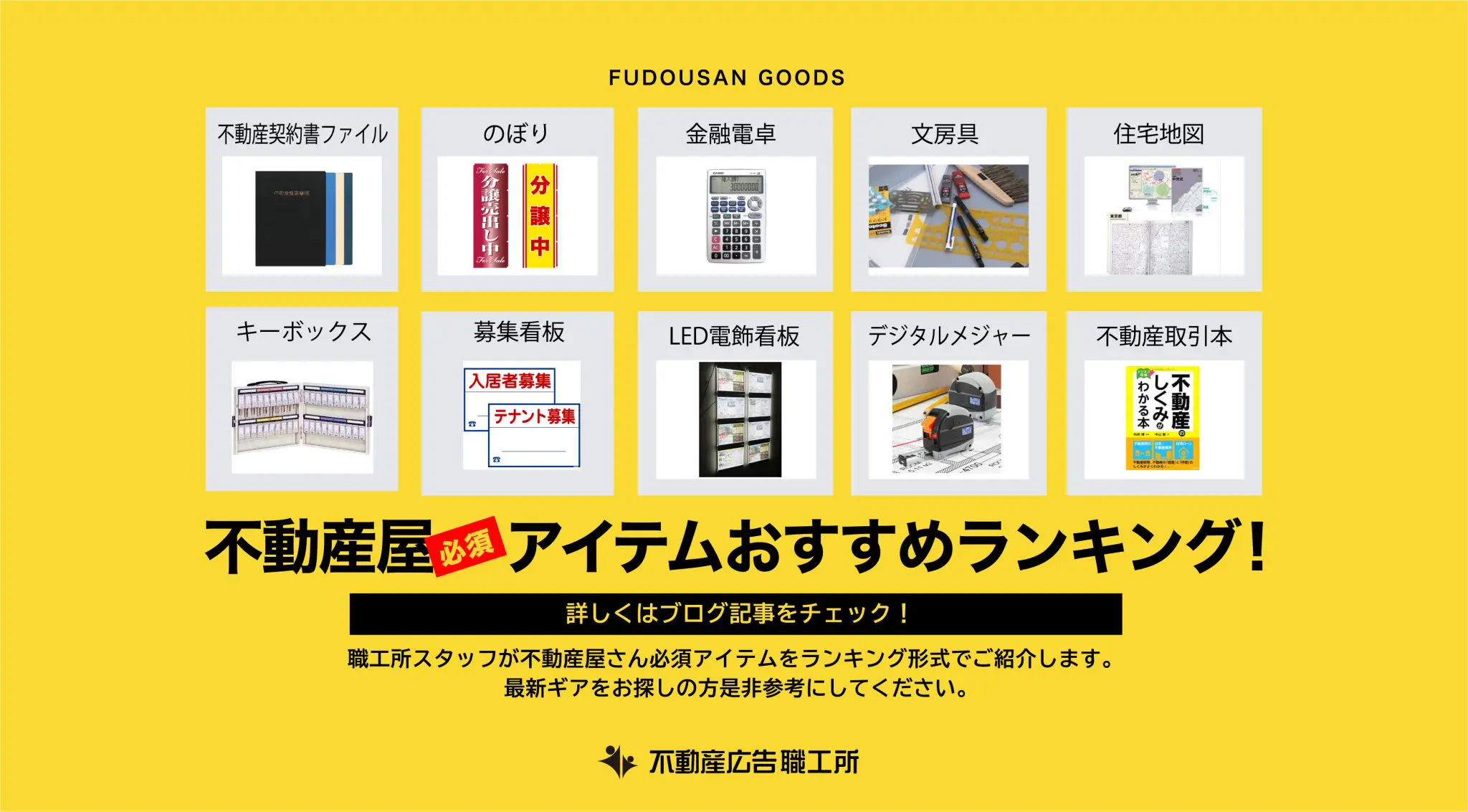有形文化財のうち文部科学大臣が重要だとして指定し、官報に告示されたものをさします。そのうち、特に優れたもの国宝に指定しています。
尚、重要文化財は建造物と美術工芸品とに分けられています。
建造物の重要文化財の約9割は、江戸時代以前の城郭や寺社などで占められています。残りの1割は明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物などになっています。また伝統的な民家については、数が減り始めた1960年代から積極的に重要文化財に指定されるようになりました。
重要文化財で、その現状を変更したり、保存に影響がある行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を得る決まりとなっています。(文化財保護法第43条)。
ただし、非常災害のために必要な応急措置であったり、維持の措置などの現状変更に限っては許可を待たずに処置を施すことが許されています。また保存に影響を及ぼすような行為についても、影響が小さなものであれば、許可を得る必要はありません。(文化財保護法第43条)
建造物と美術工芸品の件数については、文化庁ホームページを参照して下さい。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)